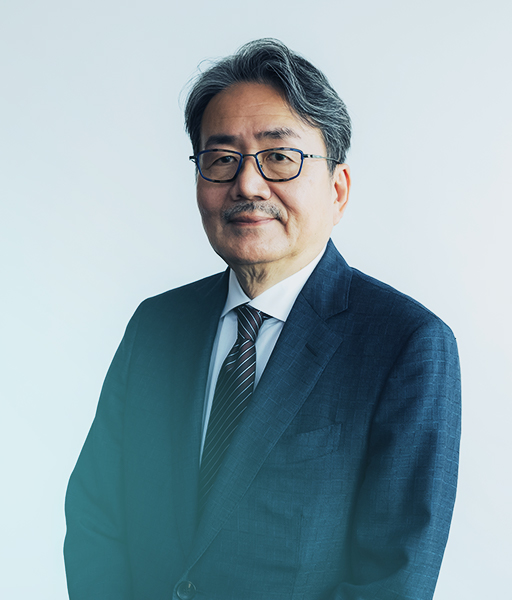2024.02.20
なんのためのエンゲージか
20年以上前、多国籍企業で働くようになって、エンゲージメントという言葉を知った。毎年、エンゲージメントサーベイの結果が国別にフィードバックされ、自国の数字改善に向けた行動の報告・共有・実践を強いられるという行事には辟易しつつも、多国籍の経営を統制する単純でオペレーショナルな手法にはなるほどと感服。各国従業員の「心情」の定量把握として、社員満足度とかモチベーションではなく、あくまでも組織成果に結果する(といわれる)エンゲージメントレベルを測るという点も、さすが業績指向のスタンスとして新鮮に感じた記憶がある。 当時、我々が受けていたサーベイでは、エンゲージメントレベルは以下の4つの総合設問で測られていた。 ・I speak highly of my organization's brand and services. ・I would recommend my organization as a great place to work. ・I feel motivated in my current job. ・Overall I am satisfied with my current job. それに対する相関性を診るための設問群が、Global & Local Sr. Leadership 、Recognition & Reward、Culture、Work Environment、Immediate Manager といったカテゴリーで用意されていた。5,6年前から、日本でもエンゲージメントの大事さが喧伝されるようになって、そのサーベイもさまざまに提供されているが、だいたい構造はこの頃のものと変わらない。何がエンゲージメントを高めるかについても、ドライバーはすでに明らかになっている。その具体表現は論者や研究者、サーベイ会社によって異なるものの、結局のところ、従業員がいだく3つの「実感」に集約できる。 有意義感 貢献実感 成長実感 ひらたくいえば、 ①目の前の仕事の意義(会社にとっての/社会にとっての/自分のキャリアにとっての)がわかっていて ②承認や報奨で自身のなしえたことの価値が確認でき、③仕事を通じての成長が実感できている、ということである。ゆえに、これら実感を喚起できれば、エンゲージメントは高まる。 さて、冒頭「組織成果に結果する(といわれる)エンゲージメントレベル」と書いた。人々が、エンゲージされて働くことで、高い意欲と主体性をもって目の前の業務に臨み、パフォーマンスを上げ、組織の生産性向上に資する、とされる。ひいては、企業価値(=経済価値)向上につながるゆえに、今年始まった人的資本情報開示でも、KPIの一つとしてエンゲージメントレベルを記載する会社は多い。 要は、「皆が自ら頑張って働き成果あげてくれる」から、いうことだが、その限りではエンゲージメントの効用としてずいぶんと矮小なのではないか。たとえば、中国語で「頑張れ」を「加油」というがごとく、良い燃料を入れることで機械を最大稼働するかのような印象だ。機械ならぬヒトが働くとは、決められた業務を遂行するのではなく、やるべき業務を考えだす=業務創造にこそ本領がある。そうした、人が「考え、創り出す」行動こそをドライブするのがエンゲージメントだ、と考えたほうが腑に落ちるし、元気がでる。 実際、組織論や人材マネジメント論の領域では、エンゲージメントの向上が創造性発揮に直結する原理はあきらかにされていないものの、エンゲージメントが創造性発揮に寄与する可能性が、多くの研究者に指摘されている。また、エンゲージメントの語源、仏語の「アンガーシュマン」は、サルトルの自由と創造に関わる言及によってよく知られている。サルトルは、アンガージュマンを通じて、人間は自由を行使し新しい価値や意味を生み出し、社会を変革していくべきだと主張した。ここでは、自由な意思をもつ人々を創造へむけ駆動する鍵としてアンガージュマン=エンゲージメントが語られていたように見える。 資本主義社会の発展とは、差異の創出(=イノベーション)により駆動されるものとシュンペーターは言ったが、企業において差異を生み出すのは、モノでもカネでもなくヒトという資源。ヒトが差異を創出するための、つまり人々が創造性を発揮するための鍵がエンゲージメントとしたほうがダイナミックだし、それこそが人的資本経営のKPIにふさわしい。 エンゲージメントが従業員の創造性を喚起するものだとすると、先の3つの実感のなかで、「有意義感」こそが、もっとも重要になるはずである。発達心理学でいう「人は目標の意味に共感し意欲を持つとき最大に能力を発揮する」からだし、そもそも創造という行為は、役割とか任務といった受け身でできることではなく、「みずから成したいと思う目的への没頭」がなければ始まらないからだ。 やるべきことの意義を自分事として確信することが、創造性発揮にむけ人々をエンゲージする。であれば、イノベーションのためには、会社の目的、事業の哲学、仕事の意味を、人々を触発し得るものとして提示できるか否かが、まず問われてくるだろう。エンゲージメントサーベイは、その検証の第一歩なのである。