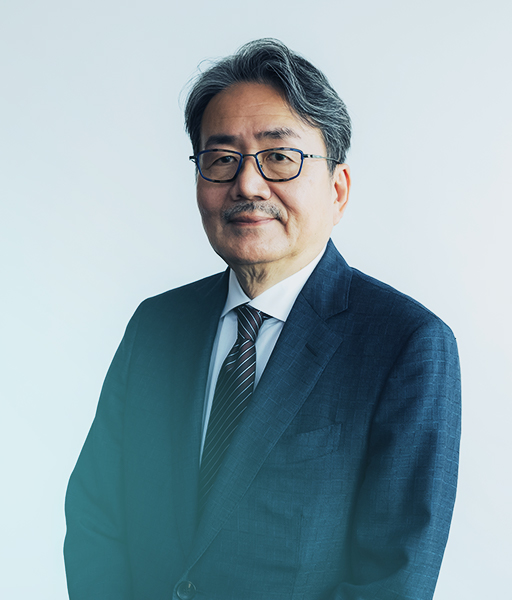2025.09.12
「内省の強制」から始める(育成のためのアセスメント②)
「管理職の登用審査」に使われるアセスメント(=アセスメントセンター方式)を、「管理職候補者の育成」に使うことを前回提案した。アセスメントの利点である客観的な保有能力判断を用いることで、的確に管理職レディネス(=管理職になる準備ができている状態)の醸成が出来る。管理職手前の早い段階で、管理職能力として何が足りないかがわかれば、その後、個別計画的なOJTやOff-JTを組むことで能力伸長や弱点補強ができるからだ。 例えば、把握された強み弱みを踏まえて、上司が、その部下を管理職にすべく育成計画を組み権限移譲を含むOJTをすればいいし、共通して足りないスキルがあれば研修を組む、といった対象者の弱点の実態に即した効果的で計画的な管理職候補者育成が可能になる。 その際にもっとも大事なことは、まずは、本人が自身のアセスメント結果を「自分事」として腹落ちすることである。「分析力」はわりと良い点とれてるが、「創造力」はぜんぜんだめだな。「人材育成力」はイマイチの点だったな、などとテスト結果に一喜一憂するだけでは、まったく意味がない。自分事としての腹落ちとは、①問題に対して自分がどう答えたからこの評価点になったのだと「理解」し、②たしかに日常業務でもこの点は弱みだなと「納得」し、③是正のためにどう「行動」するかがわかっている、ということである。 この、①理解→②納得→③行動、を本人任せにしないで、きっちりとフィードバックを行うこと。いわば、「内省の強制」のイベントとしてのフィードバックが、アセスメント以降の育成の出発点として必須だと強調しておきたい。 それには、二つの方法がある。ひとつは、アセッサーによる個別フィードバック面談。実際の評定者だから、評点の理由はきわめて具体的に説明できる。加えて対話のなかで、本人の違和感や日常の課題感を聞き、演習行動との関係を意味づけさせることで、結果の腹落ちを促す。つまり、自身の業務の文脈でアセスメント結果を再確認させ、具体行動に結びつけることが、フィードバック面談の目的となる。 もう一つは、受検者集合型のフィードバックセッションだ。こちらは、ワークショップ形式なので個別面談のようなきめ細かさには劣るが、グループダイナミクスならではの「気づき」効果の大きさに優れる。たとえば、インバスケット演習であれば、いくつかの案件について、自身の回答を手元にもって、正解に向けてのグループ討議をする。講師の「この案件では何が問われ、どうすべきだったのか」という解説とともに、他者がどう考えどう行動したかを目の当たりにすることで、自身の不足や課題に如実に気づかされる。仮に、同じ管理職を目指す立場として、どうも自分は劣っていると体感したとしたら、その焦りは、以降の自己啓発の原動力にもなるだろう。 このセッションでは最後に、自己確認した能力課題に対して、以降の改善行動方針を作らせるが、そこでも、共有のなかで他者の方針に触れることで、自身に足りない視点に気づき、方針のブラッシュアップの場となるという効用もある。セッションを通じて、他者との考え方や着眼の違いに直面することが、ときに危機感をもった自己課題への気づきをもたらすわけである。 自分の能力課題は何なのか、それをどう解決するか。その切実な理解と自己啓発の意思がなければ、上司が考える計画的な指導も、きちんとした方法論やスキルの教育も、十分な効果は望めない。いま管理職としてなにが足りていないかが自覚できていて、それをどう解消していくかの意思と方針をもつこと。それが、管理職レディネスを高めるために不可欠な第一歩なのである。 「育成のためのアセスメント」を考えるコラム2回シリーズ。 「管理職レディネスをどう高めるか」(育成のためのアセスメント①) 「内省の強制」から始める(育成のためのアセスメント②)→今回 ※育成のためのアセスメント「スマートアセスメント」はこちら