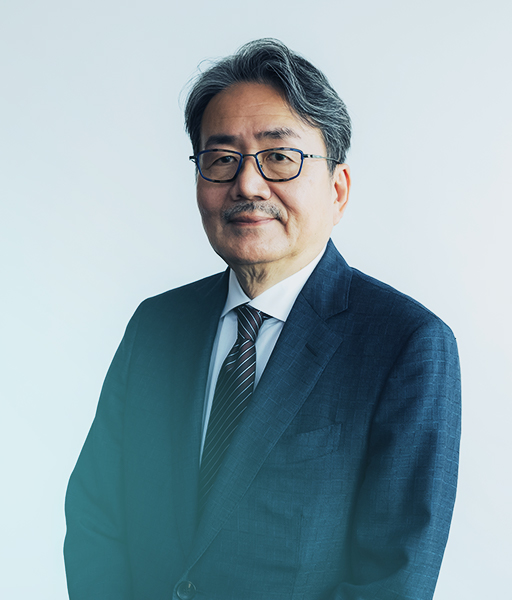2017.11.20
宴席の闘い
呑めないムキにはしんどいが、酒好きには愉しい、宴席続きの季節がやってきた。 酒を“酒として”愉しむようになったのは、40歳を超えてからだ。今思うと、20代のころは、間違いなく酒自体を味わってはいなかった。人と酒を飲む状況がただ面白かっただけである。他愛ない話で盛りあがり、笑い、たまに泣きや怒りがあるも結局は酔っぱらって沈没する馬鹿馬鹿しさが楽しかった。 そんななんでもありの酒宴でも、一つだけ許せないふるまいがあった。「まあまあ、ほらあけて」などと言いながら、無理やり酒を注ぐ輩である。概して酒が弱いメンツがターゲットになったりするから、そこに会社の上下関係があれば、ある種のパワハラである。こうした不快な輩に対しては、ゲリラ戦を仕掛けることにしていた。 注がれた酒を飲むふりをしつつすきを見て脇の植木にでも飲ましてやって、グラスを空ける。すかさず注がれれば、「礼儀として直ちに注ぎ返す」を繰り返して、その当人を泥酔させ潰して差し上げるのである。えてして、宴席パワハラ男は、酒に強いことだけがよりどころなので、ギブアップさせたところで「え、もう飲めないの? まだまだ、これからじゃない」などと言ってあげれば、もう二度と誘ってこなくなるのだった。 こんな禁じ手は別にしても、文字通り勝負というような宴席もある。たとえば、商談中の顧客との飲みの場だ。かつて同僚だった営業部長は、商談の最終局面でかならず宴席を設けた。彼の目的は、接待の場で成約を促すべく歓待すること、ではまったくない。表面的には「接待」をきわめつつ、見事な運びをもって相手が酔い潰れるまで飲ませ、介抱し、ともすれば家まで送り届けることであった。男同士の間では、たかが酒、されど酒である。「どちらがえらいかをわからせてあげればいいんだよ」と彼はいつも嘯いていた。 こうしたわかりやすい勝負ではない、孤独な闘いもあることをあるときに知った。それは、30代のころ在籍していた会社の同僚10人くらいで飲んでいたある時のことだった。なみなみ注がれたビールグラスにいつまでたっても口をつけない男がいたので、聞いてみた。 「あれ? 飲んでないけど酒だめだったんだ?」 「何言ってんの、大好きだよ。だって注いでくれないから」 あ、ごめんごめんと、注ごうとすると、まだ入っているから言って、口をつけようともしない。このやり取りが何回か繰り返されて、彼は、あきらかに一滴も飲まないまま宴席は終わったのだった。もう一回、また別の男で同じ光景があった。言い方は別だったが、本人は酒好きといいながら、実際には一切口にしないという点は、まったく同じだった。そして、この二人には、見事な共通性があったのである。 ふたりとも、詐欺師だったのだ。一人は、結婚詐欺、もう一人は金銭詐欺、ともに詐欺常習犯だった。実は、一人目の男の詐欺が露見して何年かあとに、もう一人の「飲まない男」に出会ったので、もしやと思って調べてみたら案の定で、結果、被害には合わずに済んだのだった。人を評価する、まったく新しい判断基準(かもしれないもの)をこの時知った。 嘘をナリワイとする人たちにとっては、なるほど酒は厳禁だろう。少しでも酔ってしまえば、組み上げた虚構の一角を不覚にも崩してしまうかもしれないからだ。であれば、「自分は酒が飲めない体質」といえばよいのに、そこをまた嘘のやりとりというきわどい闘いを挑んでしまうのが、さすが詐欺師の本能と感服したのだった。