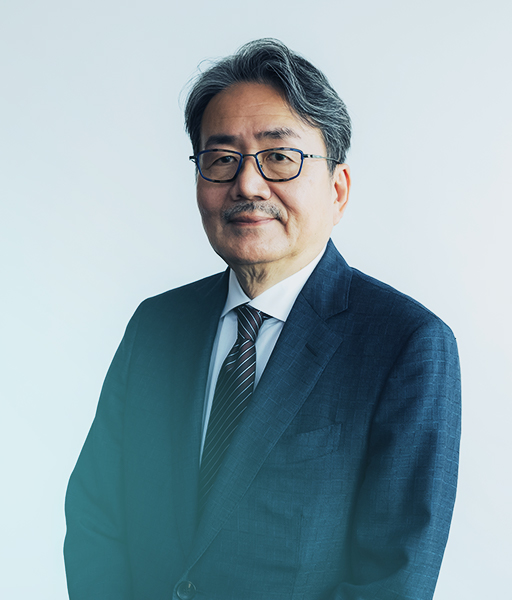2018.10.01
人を好きになるスキル
経営幹部育成のアセスメントとコーチングで定評ある人物がいる。アセスメントの結果明らかになった強みと弱みをベースに、強みを伸ばし、弱点を克服すべく、定期的なコーチングをしていくのだが、この人の凄さは、強みのまったくない、いわば箸にも棒にも掛からぬ人材であっても、明らかな成長を結果させることだ。 いったいいかなるワザを使うのか。聞くと、「要は、徹底した褒め殺しなんだよね」と笑って答える。さて、よくいわれる、褒めて伸ばすのポイントは、やみくもに褒めるのではなく、本人もよくできたと思っているあたりをきちんととらえて褒めることである。しかし、箸にも棒にも~~の人物であれば、できたと思えることがらを探すこと自体が難しい。そこをいかに褒め殺すのか。 いわば、褒める点がないのに褒めるということである。「それはねぇ、ふつうに褒めてもまったく届かないし、効果ない。ただね、褒めてくれる相手が、本当に自分のことを好きで褒めてくれるとなれば、がぜんやる気になるんだ」と彼はいう。褒められるはずもないのに、おためごかしでなく褒めてくれる、その本気さは、自分への好意に裏打ちされているからこそ伝わる。そこで素直に期待に応えようと頑張るということである。 「だからさ、まず、その人を好きになるんだよ」とその秘訣を語る。しかし、好き嫌いなんて生理的な感覚を、意思をもって制御できるんだろうか。ありていにいえば、コーチングのプロとして成果を出すために、その人を好きになる。しかも、本気で好きにならなければ、効果はないのだ。仕事のためとはいえ、「この人を好きになろう」と決めて好きになるなんて、器用なことができるのか。 と疑問を呈すると、「それができなきゃだめでしょ。そもそも部下を好きになるスキルこそ、管理職者がもつべき基本スキルなんだから」と彼は答える。では、好きになるにはどうするか。「そのためには、まず、その人をひとりの人間として認め、その人ならではの人となりに興味をもつことだ」と続けた。 なるほど、好きになるとは言葉の綾で、まず第一に、その人そのものを認める、というか畏敬の念を持つことが大事なのだ。能力とか出来不出来とか性格的問題とか以前に、ひとりの人間としての尊厳に敬意を払うことができれば、その態度はおのずと自分への好意としてうけとられるのだろう。 例えば、医療現場でよく語られる医者の基本姿勢というものがある。医者が投薬をするとき、なぜその薬が必要かを説明する。ともすれば、専門家の助ける人=医者と、素人の助けを求めている人=患者の関係のなかで、一方的なコミュニケーションになることが多い。しかしその際に、なにより患者自身の意思や納得感を尊重して、つまり畏敬の念をもって接することがいちばん大事で、それにより、投薬効果も高まるといわれている。 そういえば彼から、人を切り捨てるような言い方を聞いたことがない。悪口や批判はいうけれども、あたたかい。どんな人にも、人としての尊厳、平たく言えば、それぞれの来し方行く末に対して敬意を払い、かつ、その個別性をなにより面白がっているように見える。そう、その人を面白がる=興味を持つ、これが第二のポイントなのである。 「人に興味を持つ」というと、もうひとり思い出す人物がいる。もう20年以上前のころだが、優秀な管理職者だなぁと常々感心していた取引先の課長がいた。会社もその課長の管理能力を高く評価していて、どこの部署でも鼻つまみ者になる問題社員ばかりが彼の課員として次々送り込まれてきていた。そこでちゃんと「再生」させるのが見事だったが、いかにもたいへんな仕事だな、と思って、その苦労を聞いてみると、愉しそうにこう言った。 「いやすごく面白い。コイツは、ここを押すと、動く気になる、アイツには、この言葉が響く、とか、みんな違う。それぞれのスイッチを探し出していくのがたまらない醍醐味なんです」