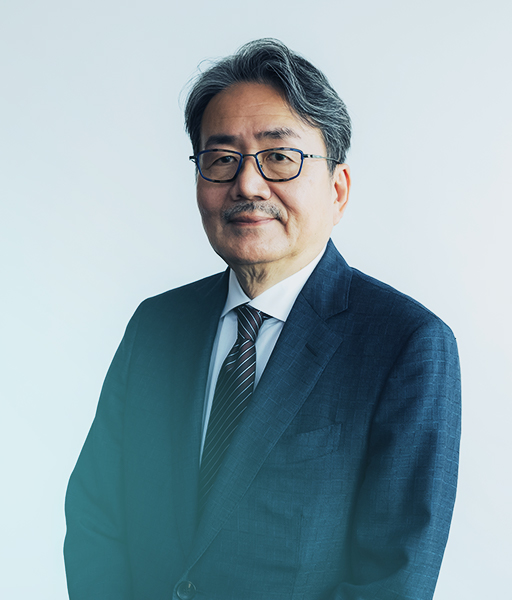2016.01.13
フェミニンリーダーシップ
ふたたび、ジェンダーについて書く。 ダイバーシティマネジメントを体現する人材活用の一環として、女性管理職比率を目標設定することがある。それについては賛否両論あって、否定派は、一定数の女性管理職登用を目指すがゆえに、本来の登用基準より低い“女性用基準”が生まれることを危惧する。ひいては、女性の尊厳を傷つける施策だとまで言うむきもある。 しかし多少無理はしても、一定比率の女性管理職を人数枠設けて“外形的に”作ることが早道であることは確かだろう。女性の管理職候補者が育ってきてから同じように選考して、などと言っていたら、女性の管理職が増えるのがいつになるかわからない。だからこその強引な目標設定だったのだから。 そこでの主たる懸念は、このように登用した女性管理職が管理職としてパフォーマンスをちゃんとあげられるか、ということだが、その心配はあたらないのではないか。きっと女性たちは、管理職能力を発揮できるはずだからである。 ある時期から、採用担当者の方々からこんな悩みを聞くことが増えてきた。選考過程で、評価の高いほうから採用していくと、女性ばかりになってしまうので、男性を採るために採用基準を下げざるを得ない、と。これはこれで大丈夫か? という気もするが、それは置くとして、優秀で元気な女性が会社に入ってきている時代である。我々も、研修の場で、女性のほうが自由で創造的な発想をする場面を何度も目撃している。 いやいや確かに女性社員は優秀だけれども、管理職としての能力はどうだろうか、と疑問を呈する方もいるだろう。それなら優秀な女性社員の業務遂行ぶりをよく見てほしい。彼女らの特長は、複数の並行作業の優先順位づけと割り切り、判断の速さである。 仕事も家事もこなすために、定時退社や場合によっては時短勤務を必須として、効率的にかつ割り切った判断で仕事をする。よく言われるようにそもそも家事というシャドウワークは、マルチタスクの並行処理であるから、仕事においても、男性社員のようにうだうだ思い悩まずに進めていくクールさがある。 管理職の仕事の大半は、多種多様な案件の意思決定である。優先順位の高いものから、早く、的確に判断する仕事である。そこには冷徹な割り切りもしつつ、やるべきことを粛々とやっていくことが求められる。かつて女性ならではのリーダーシップを分析し話題なった本『フェミニンリーダーシップ』(マリリン・ローデン)を持ち出すまでもなく、こうした管理職業務が女性に向いていないとはとうてい思えない。問題は、女性の管理職能力ではなく「管理職志向のなさ」にあるにすぎないのだ。 アセスメントセンター方式による昇格アセスメントでは「インバスケット」というシミュレーション演習を使う。管理職の立場でたくさんの案件を短時間で処理するという判断ゲームで、純粋に管理職としての意思決定力を診断するものだ。純粋に、という意味は、会社固有の暗黙知や職場の人間関係や業務情報の多寡によらずに、ということである。 従来の、人事考課の結果と部門長推薦と役員面接による登用決定だけでは見落とすかもしれない管理職能力を診るために、アセスメントの活用が増えてきている。同時に、そうした従来型の登用方式が女性の管理職登用を阻害してきたものでもある。アセスメントによって、予断なく純粋に管理職能力を見極めれば、女性管理職の登用にさほどの無理はなくなっていくだろう。 もちろん、管理職に必要なものは、ここで書いてきた意思決定力、つまり管理能力だけではない。リーダーシップと言ったり、人間力と言ったりする人々に影響を与える力がないと人はついてこないし、管理職としての強い役割意識もまた不可欠だ。それらについての女性たちの適性はまだわからない。もし多くの女性が管理職になりたいと思わないのであれば、その姿勢やマインドからして、このあたりはあるいは不得意かもしれない。 しかしそれも心配はないのではないか。管理職とは役割であって、演じるものである。男性よりも演技に長けているのが女性だという通俗的な女性観が正しいとすれば、リーダーとしての役割を、割り切って演じられるはずだから。