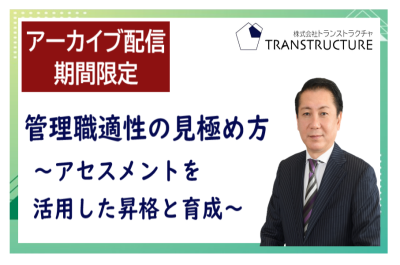執筆コラム
books

2025.09.11
思考力はどうやって高める?
現代社会は、DX化やグローバル化の進展、社会構造の変化により、将来を見通すことが困難なVUCA時代だと言われます。このような不確実性の高い環境において重要なのは、既存の知識を単に記憶・再生する力ではなく、溢れる情報を取捨選択し、論理的に組み立て、自らの判断や行動に結びつける「思考力」です。思考力は特定の職種に限らず、社会人としての実務全般において求められる基盤的能力といえるでしょう。この思考力を高めるための具体的な方法を五つの観点から考察します。 「問い」を立てる力 思考の出発点は「問い」にあります。日常業務で提示された知識や事実に対して、「なぜそうなるのか」「他の可能性はないのか」と自らに問うことで、思考は深まります。問いを持たない学びや仕事は、表面的な理解や作業にとどまりやすく、応用が利きません。カントが「批判的精神」を重視したように、前提を疑い、問い直す姿勢は思考力の根幹を成します。 言語化による思考の整理 思考は言語を通して初めて明確になります。頭の中で考えているつもりでも、それを文章や発話に落とし込んでみると、不明確な点や論理の飛躍に気づくことが少なくありません。日常的にノートに書き出す、レポートとしてまとめる、あるいはディスカッションで発言することは、思考を外化し、自己検証するための重要な過程です。言語化と内省は思考力の深化に不可欠です。 多角的な視点に触れる 思考力を鍛える上で不可欠なのが、多様な視点を取り入れることです。同じ事象でも立場や背景が異なれば解釈は大きく変わります。たとえば企業活動を経済学の視点から見る場合と、社会学や倫理学の視点から見る場合では、着目点や評価は大きく異なります。異なる分野の文献を読む、異業種の人と議論するなど、積極的に「異なる視座」に触れることは、固定的な思考パターンを崩し、創造的な発想を促します。 正解のない問題に取り組む 思考力は、単一の正解が存在する問題だけに取り組んでいては十分に鍛えられません。現実社会では、複数の解答がありうる「オープンクエスチョン」に直面することが多くあります。例えば「革新は個の天才から生まれるのか、チームの協働から生まれるのか」「持続可能な経済成長は可能なのか」「リーダーシップとは一体何か」といった問いは、明確な結論が存在しません。これらの問いに対して、多様な情報を集め、仮説を立て、議論を重ねることが、複雑な課題に対応するための思考力を養います。 思考のための時間を確保する 現代人は情報の洪水の中で、常に処理と判断を迫られています。その結果、じっくりと考える時間が奪われがちです。しかし、思考力を鍛えるには「思索のための時間」を意識的に確保する必要があります。通勤中や就寝前に数分でも構いません。あるいは一日の中で「熟考するテーマ」を定めることも効果的です。思考は筋肉と同じく、継続的な鍛錬によって強化されるものだからです。 思考力は、生まれつきの才能ではなく、習慣と訓練によって磨かれる力です。「問いを立てる」「言語化する」「多様な視点に触れる」「正解のない問題に挑む」「時間を確保する」。これらの営みを日常的に積み重ねることで、思考はより深く、柔軟で創造的なものへと進化するのです。社会での実践において、自らの思考力を鍛え続けることは、変化の激しい時代を生き抜くための最も確かな資産となるでしょう。 以上

2024.04.25
令和維新の年になれるか
現代の人事制度の基礎は明治維新と言われていますが、この明治維新は、西暦1868年(辰年)に始まり、明治天皇が即位して江戸幕府が倒れ、明治政府が発足した日本の歴史的な転換期であったわけです。 人事制度に関しては、この明治維新以降に大きな変化がありました。例えば、前近代的な身分制度からの解放や、新たな近代的な役職や制度の導入などが行われました。これらの変化は、日本の近代化とともに人事制度にも影響を与え、近代的な組織や制度の基礎を築くことになりました。 以降、辰年からどのような出来事があったか気になり整理すると、、、 1916年(辰年) 大正時代に入り、日本は急速な近代化を遂げました。官僚制度や公務員制度の改革が進められ、官僚の選任や昇進に関する基準が見直され、近代的な人事制度が整備されました。 1940年(辰年) 昭和時代に入り、日本は軍国主義の台頭や第二次世界大戦の勃発など、大きな社会変動を経験しました。この時期には、国家の体制や組織が変化し、人事制度もそれに応じて変化しました。 1964年(辰年) 戦後の高度成長期に入り、日本は経済成長を遂げました。この時期には、企業や官庁の組織が拡大し、人事制度も組織内の人材育成やキャリアパスの整備が重視されるようになりました。 1988年(辰年) バブル経済の到来やグローバル化の進展など、様々な経済・社会の変化が起こりました。これに伴い、企業や官庁の組織が再編され、人事制度は働き方の改革や労働条件の見直しなどが進められました。 2000年(辰年) バブル経済の崩壊後の経済不況期であり、企業のリストラクチャリングや人員削減が進行しました。多くの企業が人事制度の見直しや労働条件の改善を図り、労働市場の柔軟性の向上や非正規雇用の拡大が進んだ時期でもあります。 2012年(辰年) リーマン・ショック(2008年)をきっかけとする世界的な金融危機以降、多くの企業が経営環境の厳しさに直面し、人員削減や組織再編が相次ぎました。この時期には、企業の経営戦略や人事制度が大きく変化し、労働市場の不安定化や労働条件の悪化が懸念されました。 これらの過去辰年における社会的・経済的な出来事は、人事制度に影響を与え、企業や組織がその時代の課題やニーズに対応するために制度の改革を行ってきた経緯があります。特に、リストラクチャリングや経営戦略の変化、働き方の見直しや労働市場の変動への対応などが重要なテーマとなってきたのです。 今年2024年は辰年ですが、新型コロナウイルスの世界的な流行によるパンデミック以降、多くの企業がリモートワークやテレワークなどの柔軟な働き方を導入し、働き方の在り方や人事制度が大きく変化してきています。また、経済の不確実性や雇用の不安定化も影響し、労働市場全体のダイナミクスも変わってきています。 社会全体でも多様性と包摂性の重要性が認識される中、企業も多様な人材の活用や包摂的な職場文化の構築に力を入れています。人事制度も、ウエルビーイングと多様性と包摂性を推進するための取り組みを進めていく必要があります。これらの要素が、2024年(辰年)における人事制度の基礎を形成していくでしょうし、企業は、これらの変化に迅速に対応し、より持続可能な人事戦略を構築することが求められています。 今年を明治維新のごとく令和維新の年にできるかどうかは、各企業の変革の本気度にかかっているのです。

2023.11.06
ノーレイティングの時代は来るか
先日、アメリカ企業に20年勤めていた知人が日本に戻り、日本企業に転職した際に人事評価にまだMBOを使用していることにびっくりしたという話を聞きました。 このMBO(Management by Objectives and Self Control)は、アメリカの経営学者ピーター・ドラッカーによって提唱され、日本に上陸したのは意外と古く1960~70年代と言われています。その後1990年代から多くの企業で導入され現在も広く使用されていますので、もう30年程度使用されていることになります。また現在、日本で導入されているコンピテンシー評価もアメリカ発祥の手法です。 これは人事評価やパフォーマンス評価の一環として使用され、社員の強みや改善のポイントを特定し、組織全体の目標達成に貢献するために役立つものとして使用されています。 前出の知人によると、アメリカでは人事評価そのものが廃止されていて、それは2010年頃からの動きとのこと。それまでは、社員個々の成果(業績)に基づき、事実ベースで評価を行い、結果に報酬を結びつけるというものが主流でした。ただ、現在の業務遂行においては多種多様なスキルが必要なことや、目に見える成果(業績)だけで判断することが難しくなってきたことが挙げられ、人事評価を撤廃する動きが急となったそうです。 人事評価を撤廃?と聞くと人事評価を行うことをやめたのかと思う方もいるかもしれませんが、人材や企業の成長を促すうえで、評価を行うこと自体をやめることはできません。人事評価をやめるというのは、人材に点数やランク付けをやめるということです。 本来、人事評価は社員のモチベーションを上げ、成長意欲や会社への貢献度を上げていくための人材育成ツールであるにもかかわらず、評価点数やランクが思ったより低く、逆にモチベーション低下を招いてしまったなんてことがあるのです。 そこで、アメリカでは「ノーレイティング」という手法に切り替えた企業が多く、GoogleやMicrosoft、Adobeをはじめ、有名な大手企業も取り入れています。 ノーレイティングは点数で評価を行うのではなく、目標に至るまでの行動内容、どのように目標を達成したのか、目標の見直しは行われたのかといったことも含め「面談」をこまめに行うことで人事評価を行います。また、ノーレイティングは行動改善なども評価の対象とするため、チームのコミュニケーションが取れ、改善するべき点が浮かび上がりやすくなります。また、業務遂行中にフィードバックなどを行うことにより、年度末にまとめて行っていた評価者の負担も軽減といったメリットもあります。 ここまでの流れでいうと、日本にはアメリカの人事評価の手法を取り入れる傾向が顕著で、今後日本でも人事評価がなくなっていくのかと思うかもしれません。しかし、今の日本で人事評価をすぐに撤廃することは難しいでしょう。日本では、アメリカですでに多くの企業が行っているタレントマネジメントが浸透しきっていないことが挙げられます。 日本企業は伝統的な組織文化を持っており、ヒエラルキーが強調され、社員のスキルや成果を評価するといった文化があります。このような文化では、タレントマネジメントが十分に評価されず、個人の成長と適材適所の配置に焦点を当てるのが難しいのです。 ノーレイティングは、数値評価や従来の評価スケールに頼らず、社員の個々の成長と発展に焦点を当てます。タレントマネジメントは、社員のスキルやキャリアの目標を明確にし、それを支援するためのプランを策定するプロセスです。これを組み合わせることで、社員の成長をより効果的に促進できるのです。 タレントマネジメントを導入するには、社内の現場や部門・部署を超えての連携が不可欠となります。そのため、タレントマネジメントが行き届いてからでないと人事評価を廃止・簡易化するのは難しいのではないでしょうか。 ただ、日本でもグローバルなビジネス環境の変化や若年層の価値観の変化により、タレントマネジメントの重要性が認識されつつあり、いくつかの企業では取り組みが進んでいます。何年後かには導入が進み、タレントマネジメントが当たり前の企業が増え、ノーレイティングを前向きに導入する時代が来るのかもしれません。 以上